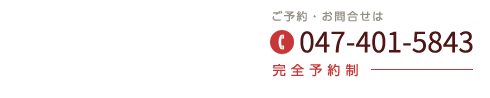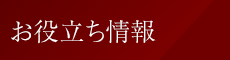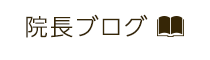GW明けは5月病に注意?
五月病は、気分が沈んだり頭がぼんやりしてしまい、ひどいと無気力になって登校・出社できなくなることもあるものです。
一般的に言われているように、5月は生活環境が変化した人たちの緊張が切れ、心身に不調が出やすい時期です。また、今年は4月から初夏を思わせる陽気になったり、5月には梅雨に近い天候になるとの予報があるように、季節が前倒しになっています。急な変化に体の対応が難しくなっているといえます。
さらに、在宅勤務やリモート授業の影響で、人と直接交流する機会が少なくなっているのも見逃せません。人は、人と集い情報交換することを好む生き物なので、知らずしらずのうちに精神的な負担となることがあります。
また、緊張感から痛みなどの不調を感じなくなっている人が、連休で緩むことにより偏頭痛を起こすこともあります。こういった影響から、急に会社や学校に行けなくなってしまうのも、広い意味での五月病といえるでしょう
本来ならば、5月の連休は疲れやストレスをリセットできるよい機会です。しかし、気分転換のつもりが、逆に心身の不調につながる可能性もあります。
五月病を防ぐための連休終盤の過ごし方
家で○○三昧だった人は・・・
→3日前から生活リズムを立て直す
趣味を楽しむのは悪いことではありませんが、生活のリズムがズレてはいないでしょうか。また、日頃の疲れを取ろうと、ずっと寝て過ごすのもよくないと言いますね。
連休明けに時差ボケ状態になるのが問題です。規則正しい生活リズムは、案外心身の健康に影響するものです。疲労が溜まっている場合、十分な睡眠で回復するのは大切なことですが、ほどほどが重要です。
連休明けからは、新入社員や新入生も仕事や学業が始まります。時差ボケ状態では、ダメージを受けやすくなってしまいます。
リズムのズレを直せるのは1日1時間くらいです。朝7時に起きるのが9時など遅くなっているのなら、3日前くらいから1時間ずつ戻していきましょう
過密スケジュールだった人は・・・
→最終日は予定を詰め込まず調整日に
旅行や遊びに出かけ、楽しさのあまり無理をしてはいないでしょうか。
旅行などでは、食事や活動のリズムが普段と大きく変わることが多いですね。
食事も、普段と違ったものを違った時間に食べることが多く、胃腸に負担がかかっています。5月は冬用の食事から夏用の食事に変わる中間にあたり、調子を整えにくいことも重なってしまいます。
連休明けに疲れが出ないよう、最低でも最終日は休み、いつもの生活に近いリズムにしましょう。旅行中でも朝ごはんをいつものと似ているものを選ぶなど、元のパターンを意識するのも効果的です。
不調の兆しがある人は・・・
→早めの対処で悪化を防ぐ
日中に軽く走ったり散歩するなど、適度な活動が良いです。
連休明けに心身の調子が崩れやすいのは確かです。崩れてしまったものを戻すのは大変なので、崩さないよう予防することが大切です。休み中も普段の生活リズムを守るのが基本ですが、前半にズレてしまったのなら今から少しずつ整え、連休明けにパフォーマンスが下がらないようにしましょう
連休明けを元気に、充実した生活が送れるよう心がけたいですね。
参考:ウェザーニュース